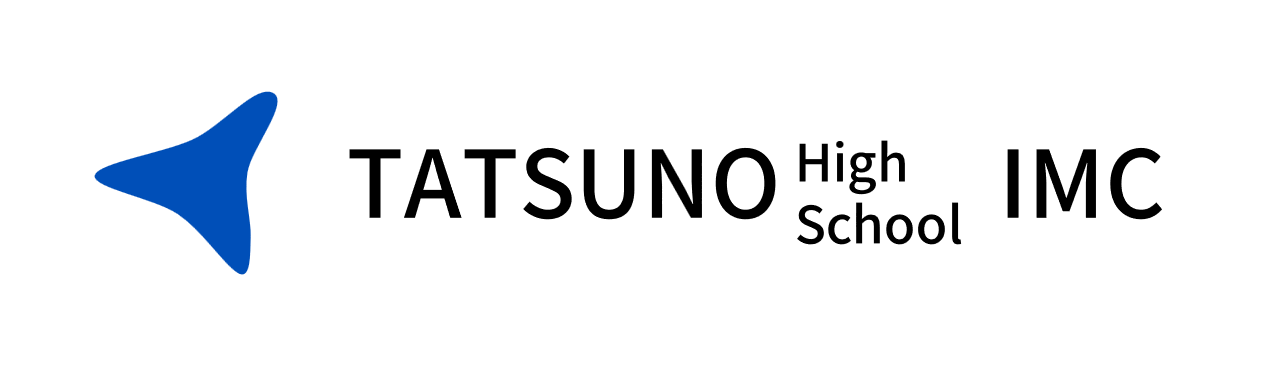こんにちは!情報班の総務を担当している者です。 IMCX連載企画、第2弾をお届けします!今回は、私たちが活動を通じて一番大切にしていること、それは「活動ノウハウをどう未来へ繋ぐか」という、チーム運営の根幹に関わるお話です。
技術や知識が途絶えてしまうと、せっかく築いた活動もそこでストップしてしまいますよね。そうならないように、どんな世代交代があっても、情報班がずっと楽しく、ずっと進化していける「持続可能な組織運営のモデル」を、今、私たちの手で確立しようとしています。
1. 記録は「未来の自分たち」を助ける魔法のツール
現在、私は情報班の総務責任者として、あらゆるプロジェクトの記録・情報集約を統括しています。班員には、活動のどんな小さなことでも「写真、ログ、試行錯誤のプロセスを必ず残してほしい」とお願いしています。
正直、現場で作業しているメンバーからすれば、「なんで今、記録しなきゃいけないの?」「流れが止まる!」と面倒がられることも少なくありません。
でも、記録の目的は、単なる「思い出作り」ではないんです。最大の目的は、「後輩や次のプロジェクトに関わるメンバーが、無駄な苦労をせずに済むようにするため」、つまり未来の活動をスムーズにするための実利的な基盤なのです。
同じ失敗を繰り返す「見えない負債」をなくそう
技術的な活動では、過去の失敗のデータや、機材の最適な設定方法が残っていないと、後任者は必ず同じ壁にぶつかります。
私たちは、この非効率な手戻りを「活動上の見えない負債(負の遺産)」だと考えています。 せっかく情報班に入ったのに、先輩たちと同じ場所でつまずいて時間を浪費するのはもったいない!記録の徹底は、この「見えない負債」を清算し、ムダな徒労を回避し、もっとクリエイティブで高度な活動に時間を使えるようにするための、大切な「土台作り」なんです。
2. 「前例」を味方につける!活動推進のための交渉術
私たち77回生は、過去の活動実績やノウハウの引継ぎが少なかったため、多くの新規プロジェクトをゼロから手探りで進めることになりました。この経験から、技術的な知識だけでなく、「組織運営に関するノウハウ」を記録することが、どれほど重要か痛感しました。
活動をスムーズにする「交渉の武器」
学校という組織の中で新しい活動を進めるには、先生方への予算申請、外部との連携の許可、実験場所の確保など、多くの手続きが必要です。このような場面で、「前例」の存在は非常に大きな意味を持ちます。
- 「去年の〇〇イベントでは、このくらいの費用で実現できています。」
- 「この機材は過去にも導入実績があるので、安全面も大丈夫です。」
このように記録を体系的に残すことで、後輩たちは、感情論ではなくデータに基づいて企画の実現性や安全性を正確に提示できるようになります。記録の体系化は、後輩たちが新しい挑戦を円滑に進めるための、最も頼れる「交渉の武器」となるのです。
3. 「誰か一人の責任」にしない!知識の属人化を防ぐ反省
今年度、情報班は「科学の屋台村」「eスポーツ大会」など、たくさんの新しい取り組みを成功させました。最初は、記録業務に特化した総務補佐2名に記録を集中してもらいました。
しかし、この体制はすぐに問題が発生しました。記録担当者が関わっていないプロジェクトや、急な技術的な試行錯誤のプロセスなど、「記録担当者の目が届かない領域」のノウハウが完全に抜け落ちてしまったのです。
これは、「知識が特定の個人に集中しすぎる(属人化)」という大きなリスクでした。特定の先輩にしか分からないことが多すぎると、その先輩が卒業した瞬間に、班全体が困ってしまいます。
私たちはこの失敗から学び、「記録は担当者の業務」ではなく、「記録は班員全員の責任であり、義務である」という組織文化へと考え方を変える必要性を痛感しました。
4. 解決戦略1:全員が情報を放り込める受け皿
属人化のリスクを解消するため、私たちは運用ポリシーをガラリと変えました。
「全員が、いつでも、どんな形式のデータでも気軽にアップロードできる、一つの大きな受け皿」の設置です。
具体的には、Google共有ドライブ等のクラウドストレージを活用し、アクセス権限を全班員に開放しました。この場所は、整理整頓を後回しにし、とにかく情報の鮮度と網羅性を優先して、加工されていない一次情報(ナマのデータ)をそのまま集積する場所です。
Googleドライブは、情報集約のハードルを下げ、「記録の空白」を防ぐとともに、後から多角的な検証や分析を可能にする、情報班の「情報の宝庫」として機能しています。
5. 解決戦略2:「Galileo」プロジェクトと「知恵のバトン」の形成
しかし、Googleドライブに集積されたデータは、あくまで素材(ナマの一次情報)です。これだけでは、後輩がすぐに活用できる「整理された知識」とは言えません。個人の経験(暗黙の知恵)を、誰もが理解できる「形式知」へと変換するプロセスが必要です。
現在進行中の「Galileo(ガリレオ)」プロジェクトは、この知識の「言語化」と「体系化」を担っています。後輩が手に取りやすく、楽しく読めるよう、単なる分厚いマニュアルではなく、図版やグラフを多用した情報誌(マガジン)形式で作成しています。
6. むすびに:情報をうまく使えるチームへ
このプロジェクトを通じて、情報班の各ユニット(事務組織)の役割は大きく変わろうとしています。単なる「事務係」ではなく、「チーム全体の知恵を生み出し、未来へ繋ぐ仕組みを設計する役」へと進化しています。
地道な活動ですが、これが情報班の未来を支える最も重要な挑戦だと信じています。次回のIMCX連載も、ぜひ楽しみにしていてくださいね!